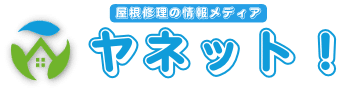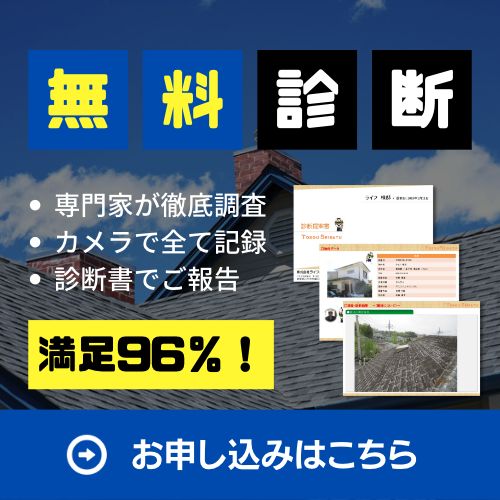日本は台風の通り道に位置しており、毎年のように強風や豪雨による住宅被害が報告されています。
特に瓦屋根は歴史ある日本建築の象徴ですが、「台風で瓦が飛ぶのではないか」「雨漏りが起きやすいのではないか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、強風で瓦がズレたり落下したりする事例は少なくなく、隣家や通行人に被害を及ぼすケースもあります。
さらに、台風後の雨水浸入によって建物内部が傷むと、修理費用も高額になりかねません。
そこで本記事では、瓦屋根が台風に弱いとされる理由や、実際の被害事例、台風前にできる予防策、被害を受けた際の応急処置や修理方法まで徹底的に解説します。
瓦屋根が台風で被害を受けやすい理由
瓦屋根は日本の住宅に古くから用いられてきた屋根材であり、重厚感と耐久性に優れています。
しかし台風シーズンになると、「瓦が飛んでしまうのではないか」と心配する声も少なくありません。
実際に、瓦屋根は台風の強風による影響を受けやすいとされており、その原因には構造的な特徴や経年劣化、施工の状態などが関わっています。
ここでは、瓦屋根が台風で被害を受けやすいといわれる理由について、詳しく解説していきます。
瓦屋根の構造的な特徴
瓦屋根は、1枚1枚の瓦を屋根全体に葺き並べる構造をしています。
瓦自体は粘土やセメントでできており非常に重く、耐久性や遮熱性に優れていますが、重さがある分、強風を受けると「てこの原理」で瓦が浮き上がりやすく、固定が甘い部分から飛ばされてしまうことがあります。
また、瓦と瓦の間にわずかな隙間があるため、強風が入り込むと瓦を持ち上げる力が働きやすい特徴があります。
強風で瓦が飛ばされるメカニズム
台風の風は、屋根の端や棟(屋根の頂点部分)に集中しやすい傾向があります。
特に棟瓦は高さがあるため、風を受ける面積が大きく、強風によって崩れたり飛散したりしやすいのです。
さらに、台風時には風の向きが刻々と変化するため、一度持ち上がった瓦が次の風で飛ばされることも少なくありません。
経年劣化や施工不良によるリスク
瓦屋根は定期的にメンテナンスを行えば50年以上持つとも言われる耐久性を誇ります。
しかし、漆喰の剥がれや下地の劣化、施工不良などがあると固定力が低下し、台風の被害を受けやすくなります。
特に築30年以上経過して一度も点検していない住宅では、見えない部分で瓦が緩んでいる可能性が高いです。
台風で瓦屋根に起こりやすい被害事例
台風が直撃すると、瓦屋根にはさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
軽微なズレやひび割れから始まり、瓦の落下や棟の崩れ、さらに雨漏りといった深刻な被害にまで発展するケースも珍しくありません。
これらの被害は放置すると住宅の寿命を縮め、修理費用も高額になってしまいます。
この章では、台風によって瓦屋根に実際に起こりやすい被害事例を取り上げ、それぞれの特徴やリスクを解説します。
瓦のズレや落下
最も多い被害は、瓦がズレたり落下するケースです。
部分的なズレであっても、そこから雨水が浸入し、室内に雨漏りを引き起こす可能性があります。
瓦が庭や道路に落下すると二次被害につながるため、早急な対応が必要です。
棟瓦(むねがわら)の崩れ
屋根の頂点にある棟瓦は、台風の風を直接受けるため特に被害を受けやすい部分です。
棟が崩れると見た目の問題だけでなく、屋根全体の耐久性が低下します。
崩れた部分から雨水が侵入すると、内部の木材が腐食する原因にもなります。
雨漏りの発生と内部の被害
瓦が飛んでしまったりズレたりすると、雨水が屋根裏に直接侵入します。
最初は天井にシミができる程度でも、放置すると断熱材や柱に水が染み込み、カビや腐食を招きます。
最悪の場合、耐震性が低下して建物全体の寿命を縮めることになりかねません。
台風前にできる瓦屋根の対策
台風による被害を最小限に抑えるためには、事前の点検と対策が欠かせません。
瓦屋根は丈夫な建材ではありますが、定期的なメンテナンスを怠ると小さな不具合が大きな被害につながる恐れがあります。
この章では、専門業者に依頼する前に知っておきたい具体的な対策について紹介します。
瓦のズレやひび割れ点検
台風シーズン前に、瓦がズレていないか、ひび割れていないかを点検することが大切です。
特に棟部分や屋根の端は被害を受けやすいため、重点的に確認しましょう。
棟部分や漆喰の補修
漆喰は瓦を固定する役割を持ちますが、経年劣化で剥がれやすくなります。
台風前に漆喰の補修を行うことで、瓦の飛散リスクを大幅に下げることが可能です。
専門業者による定期メンテナンスの重要性
瓦屋根は耐久性が高い分、劣化が目に見えにくい特徴があります。
専門業者による定期点検を受ければ、小さな不具合を早期に発見でき、台風時の大きな被害を未然に防ぐことができます。
台風で被害を受けた際の応急処置と修理方法
もし台風で瓦屋根が被害を受けてしまった場合、まずは安全を確保し、二次被害を防ぐ応急処置を行うことが重要です。
そのうえで、専門業者による調査と修理へとつなげるのが基本的な流れとなります。
被害を受けた直後に適切な対応を取れるかどうかで、被害の拡大や修理費用に大きな差が出ることもあります。
この章では、台風被害発生時に取るべき応急処置と、修理の進め方を解説します。
まず安全を確保する(登らない)
台風直後は屋根が濡れて滑りやすく、大変危険です。
自分で屋根に登って確認するのは避け、まずは安全を確保してください。
専門業者による修理の流れ(現地調査→見積もり→工事)
被害が発生したら、できるだけ早く業者に依頼しましょう。
一般的には「現地調査→見積もり→修理工事」という流れで進みます。
被害状況によっては部分補修で済む場合もありますが、広範囲に被害が及んでいる場合は葺き直しや葺き替えが必要になることもあります。
ブルーシートで雨漏りを防ぐ方法
応急処置として有効なのがブルーシートです。
瓦が飛んだ部分を覆い、雨水の侵入を一時的に防ぐことができますが、固定方法が甘いと再び風で飛ばされるため、専門的な知識が必要です。
実際の工事が始まるまではタイムラグが発生するため、工事業者に応急処置としてブルーシートを設置してもらいましょう。
瓦屋根の修理するならヤネットへ!
屋根修理業者をお探しの方は、屋根工事専門店のヤネットまでご相談ください。
無料診断をお受け頂くと、屋根修理のプロによって入念な現地調査を行うため、既存の劣化状況を正しく判断することができます。
また、劣化状況に応じて最適な修理方法をご提案致しますので、屋根修理業者の選定にお困りの方は、お気軽にヤネットまでご相談ください。
まとめ
今回の記事では、瓦屋根の台風対策のポイントについて詳しく解説しました。
記事の要約は以下のとおりです。
- 瓦屋根は重くて丈夫だが台風の強風によって浮き上がりやすい
- 台風時には瓦のズレや落下、棟瓦の崩れ、雨漏りといったトラブルが発生しやすい
- 事前に瓦の点検や補修を行うことで被害を軽減できる
- 被害発生後は安全を確保し専門業者に修理を依頼することが重要
瓦屋根は日本の伝統的な建材であり、耐久性や美観に優れていますが、台風の強風によって被害を受けやすいという側面があります。
特に棟瓦や経年劣化部分はリスクが高いため、日頃の点検とメンテナンスが欠かせません。
台風前には瓦や漆喰の状態を確認し、必要であれば補修や応急処置を行いましょう。
万が一被害を受けた場合は、ブルーシートで雨漏りを防ぎつつ、速やかに専門業者へ依頼することが大切です。
修理費用は被害の程度によって異なりますが、火災保険や補助金を活用すれば自己負担を軽減できます。
関連:屋根修理で火災保険を利用するポイント!条件から申請手順まで
関連:屋根修理で使える補助金・助成金とは?種類や事例を徹底解説!
安心して台風シーズンを乗り越えるためには、信頼できる業者を選び、計画的なメンテナンスを行うことが何より重要です。